ハイブリッドワークの導入企業事例7選!メリットやデメリット、成功させるコツを解説
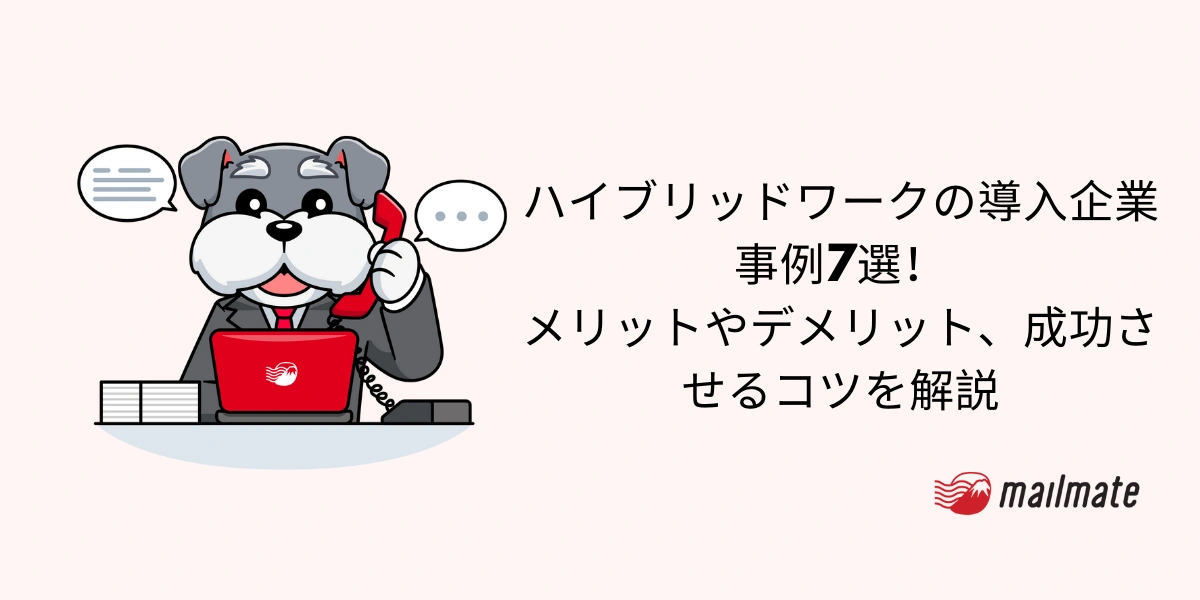
近年、働き方改革やコロナ禍をきっかけに、多くの企業で「ハイブリッドワーク」が導入されるようになりました。オフィスワークとリモートワークを組み合わせた柔軟なスタイルは、生産性の向上やワークライフバランスの改善につながる一方で、コミュニケーション不足や公平性の確保といった課題も抱えています。
実際に国内外の大手企業も積極的にハイブリッドワークを取り入れており、その取り組みは多様です。本記事では、ハイブリッドワークの定義からメリット・デメリット、導入企業の事例までを整理して紹介します。
クラウド郵便 MailMateで、複数の拠点に届く紙の郵便物をパソコン・スマホ上のダッシュボードで一括確認・管理できます💻📩 郵便物のスマート管理始めませんか?
ハイブリッドワークとはオフィスワークとリモートワークを組み合わせた働き方

ハイブリッドワークとは、その名のとおり「出社」と「在宅勤務」を組み合わせて働くスタイルを指します。コロナ禍をきっかけにリモートワーク・テレワークが一気に普及しましたが、完全リモートではコミュニケーション不足や企業文化の希薄化といった課題が浮き彫りになりました。
そこで注目されたのが、必要に応じて出社しつつ、業務の性質に合わせてリモートも取り入れるハイブリッド型の働き方です。企業にとってはオフィスコストの削減や人材確保の柔軟性が高まる一方、従業員にとっても生活リズムや家庭の事情に合わせやすいという利点があります。
近年は「柔軟な働き方」を重視するZ世代の就職活動にも影響を与えており、企業の採用競争力を高める要素にもなっています。次の項目では、こうしたハイブリッドワークが注目を集める理由についてさらに掘り下げていきます。
ハイブリッドワークを導入している企業が増加中の理由
近年、コロナ禍を経て働き方の選択肢は大きく広がり、オフィス出社とリモートワークを組み合わせた「ハイブリッドワーク」を導入する企業が急増しています。
サイオステクノロジーが2025年に実施した調査によると、65%の企業がハイブリッドワークを導入していると回答し、特に従業員数1000人を超える大企業ではその割合が87%に達しています。
背景には、従業員の柔軟な働き方ニーズや、採用競争力を高めたい企業側の事情があります。実際、Z世代の75%が「柔軟な働き方を企業選びの必須条件」と捉えており、ハイブリッドワークの有無が採用や定着に直結していることが明らかになっています。
参考:サイオステクノロジー株式会社「柔軟な働き方が企業にもたらす影響に関する実態調査」を実施」
ハイブリッドワーク導入企業の事例7選

この章では、実際にハイブリッドワークを導入している企業の取り組みを紹介します。グローバル企業から日本企業まで、多様な成功事例を取り上げることで、導入の背景や工夫点を理解できるでしょう。
SAPジャパン株式会社
SAPジャパンは「Pledge to Flex」という働き方の枠組みを掲げ、従業員に高い柔軟性を提供しています。勤務する「場所」、働く「時間」、利用する「ワークスペース」を個々の業務やライフスタイルに応じて選択できる仕組みです。
2021年の社内調査では、従業員の80%以上が柔軟な働き方を求めていると回答しており、その声を反映して大阪オフィスをリノベーション。集中作業やチーム協働など目的に応じた空間設計が進められました。グローバル基準をローカルに適応させ、日本に即したハイブリッドワークの実現を図っているのが特徴です。
富士通
富士通は「Work Life Shift」という大規模な働き方改革を推進しています。出社を前提とした勤務スタイルを改め、在宅や外部オフィスを含む多様な場所での勤務を可能にしました。特に首都圏では自社オフィスを大幅に縮小し、シェアオフィスやコワーキングスペースを積極的に活用しています。
社員は「業務の目的」に応じて最適な環境を主体的に選べるようになり、働き方の自由度が大幅に向上しました。さらに、オフィス利用状況を可視化してデータ分析を行い、成果につながる働き方を検証する取り組みも進めています。単なる在宅勤務の導入にとどまらず、組織全体で未来志向の働き方を模索している事例です。
EY (Ernst & Young)
世界的なプロフェッショナルファームであるEYは、ハイブリッド勤務をグローバルに展開しています。社員は週のうち少なくとも2日は在宅勤務が可能で、残りはオフィスやクライアント先で働く仕組みです。特定の出社日を設けず、プロジェクトやチームごとに最適なスケジュールを決める点が特徴となっています。
また、オフィスそのものも「コラボレーションを促す場所」として再設計を進めており、会議やアイデア創出に適した空間づくりが進められています。従業員の柔軟性確保だけでなく、人材確保や離職防止にも効果があり、コンサル業界全体の働き方モデルに大きな影響を与えているといえるでしょう。
日本マイクロソフト
日本マイクロソフトは、2007年から在宅勤務制度を導入しており、早くから柔軟な働き方に取り組んできました。現在では「ハイブリッドワーク」を推進し、オフィスを単なる作業場所ではなく「共創の場」として再設計しています。
Teamsやクラウドツールを中心に、リモートでもオフィスでも変わらない生産性を実現できる環境を整えました。さらに、従業員の働き方データをもとに改善を続けており、職種やプロジェクトごとの最適解を追求しています。
長年の経験から得たノウハウを公開しているため、日本企業におけるハイブリッドワークのモデルケースとしても広く注目されています。
Adobe
Adobeは「未来の働き方はハイブリッドである」と明確に打ち出し、世界各地でオフィス再設計を進めています。在宅勤務では集中作業を、オフィスでは対面での協働を行うといった役割分担を前提にした制度設計が特徴です。
リーダー層自らが柔軟な働き方を実践し、心理的安全性を担保する文化づくりも積極的に展開しています。また、社員の意見を反映してオフィスの用途を「交流・学び・創造の場」へとシフトさせており、ハイブリッド環境で最大限の成果を発揮できるよう工夫しています。
クリエイティブ産業を支える企業として、働く場の柔軟性と創造性の両立を体現している好例です。
Pinterestは、いわゆる「ハイブリッドモデル」を極端なレベルまで導入した企業として知られています。社員は原則として場所を問わず働ける一方で、オフィスを完全に廃止するのではなく「必要に応じて集まる場」として残しています。
特定の出社日を設定せず、プロジェクトやチームの状況に応じて柔軟にオフィス利用を決定するスタイルです。オフィスは協働やチームビルディングのための場として設計され、働く自由度と人間的なつながりを両立させています。
この柔軟なモデルは従業員からの支持も高く、次世代のハイブリッドワーク像を示す事例として注目されています。
Dropbox
Dropboxは「バーチャルファースト」という独自のアプローチを採用しています。これは従来のハイブリッドワークとは少し異なり、リモート勤務を基本としつつ、オフィスを「共同作業や交流のためのスタジオ」と位置づける考え方です。
日常業務の大部分はオンラインで行い、必要なときにだけメンバーが集まる仕組みを導入しました。この方針により、出社と在宅の中間に位置する新しい働き方が実現しています。従業員の移動負担を軽減しながらも、チームの一体感や創造性を確保できる点が評価されており、ハイブリッドの概念を広げるユニークな事例といえるでしょう。
ハイブリッドワークのメリット

この項目では、ハイブリッドワークが企業や従業員にもたらすメリットを整理します。
柔軟な働き方を取り入れることによる生産性向上
ハイブリッドワークの大きなメリットのひとつが、生産性の向上です。従業員が自分に合った環境で働けるため、集中力を高めやすく、効率的に業務を進められます。例えば、集中が必要なタスクは自宅で取り組み、打ち合わせやチームでの作業はオフィスで行うといった使い分けが可能です。
サイオステクノロジーの調査でも、柔軟な働き方を導入した企業の多くが「業務効率の改善」を実感しており、従業員のモチベーション維持にもつながっています。特に若い世代は、自分のリズムに合わせて働けることを重視しており、その結果として高い成果を出す傾向があります。
ワークライフバランスの改善が期待できる
通勤時間の削減や働く場所の選択肢が増えることで、ワークライフバランスの改善も期待できます。通勤に毎日往復2時間かかっていた人が週3日リモート勤務になるだけで、年間数百時間もの余裕が生まれます。その時間を家族との団らんやスキルアップに充てられるため、従業員の満足度が大幅に向上します。
企業にとっても、従業員の心身の健康が守られることで長期的に安定したパフォーマンスを得られるという利点があります。Z世代の多くは「プライベートの充実と仕事の両立」を重要視しており、ハイブリッドワークはその期待に応える仕組みとして注目されています。
ハイブリッドワーク環境を整えることで人材確保と離職防止につながる
人材不足が深刻化するなかで、柔軟な働き方を提供できるかどうかは採用力に直結します。特に優秀な人材ほど「働きやすさ」を重視する傾向があり、ハイブリッドワークを導入している企業は応募数や内定承諾率が高まりやすいといわれています。
また、既存社員にとっても「ライフステージの変化に対応できる働き方がある」という安心感が離職防止につながります。サイオステクノロジーの調査では、Z世代の75%が「柔軟な働き方を企業選びの必須条件」と回答しており、制度の有無が人材確保に大きな影響を与えていることが明らかになっています。
クラウド郵便メールメイトで、会社宛の紙の郵便物をWEB上で確認・管理しませんか?郵便物の受領・確認のための出社、保管場所が不要になります。
ハイブリッドワーク導入の課題・デメリット

メリットが多い一方で、ハイブリッドワークには課題も存在します。以下のようなデメリットについて理解しておくことも大切です。
コミュニケーション不足に陥る可能性がある
ハイブリッドワークでは、従業員同士の顔を合わせる機会が減るため、情報共有や雑談の機会が不足しやすくなります。サイオステクノロジーの調査でも「コミュニケーション不足」が63%の企業で課題として挙げられています。
リモートでは業務連絡に偏りがちで、ちょっとした相談や気軽な交流が生まれにくい点が問題です。その結果、チームの一体感が損なわれたり、新入社員や中途採用者が馴染みにくくなったりするケースもあります。企業は意識的にオンライン会議や雑談の機会を設けるなど、コミュニケーションを補う工夫が必要になります。
オフィス勤務・リモート勤務の公平性の確保が難しい
もうひとつの課題は、公平性の確保です。出社が多い人とリモート中心の人とでは、上司や同僚との接点に差が生じやすく、評価や昇進に影響が出ることも懸念されています。実際、「見えるところで働いている人が有利になる」と感じる社員も少なくありません。
また、家庭環境や住環境によってリモートのしやすさが異なるため、制度の恩恵を受けられる人とそうでない人の差が広がる可能性もあります。公平な制度運用のためには、評価基準を成果重視に変えるなど、マネジメント側の意識改革が求められます。
管理・セキュリティ面の課題もある
ハイブリッドワークでは、従業員が自宅や外出先から業務を行うため、情報管理やセキュリティ面でのリスクが高まります。特に紙の資料を持ち帰る場合、紛失や情報漏洩につながる恐れがあります。また、個人の端末や自宅Wi-Fiなどの通信環境で勤務するケースも多く、十分なセキュリティ対策が取られていないとサイバー攻撃の標的になりかねません。
さらに、社内とテレワーク環境でアクセス権限が統一されていないと、情報管理にムラが生じやすくなります。企業はVPNやゼロトラストセキュリティの導入、文書のデジタル化による共有体制の強化など、多角的な対策を講じることが求められます。
ハイブリッドワークを成功させるポイント

ハイブリッドワークを単なる「制度」として終わらせず、実際に成果を上げるためには工夫が欠かせません。本項目では、ハイブリッドワークを成功させるためのポイントを3つ紹介します。
ルールを明確に設定する
ハイブリッドワークを導入する際には、曖昧な運用を避け、ルールを明確に定めることが不可欠です。例えば「週2日は出社必須」「会議は原則オンラインで実施」など、誰もが理解できる形にすることで混乱を防げます。
ルールを定める際はトップダウンで決めるのではなく、現場の意見を取り入れることで納得感を高めることも大切です。さらに制度開始後も定期的に見直しを行い、状況に応じて柔軟に調整できる仕組みにすることが、長期的な定着につながります。
ITツールを活用する
成功の鍵を握るのは、ITツールの効果的な活用です。コミュニケーションにはチャットやオンライン会議ツール、タスク管理にはプロジェクト管理アプリを導入することで、情報の透明性とスピード感が高まります。また、出社・在宅の勤怠管理やセキュリティ対策も重要であり、専用ツールの利用が欠かせません。
特に中小企業では、導入コストを抑えつつ機能を活用できるクラウドサービスが選ばれやすい傾向にあります。これらの仕組みを組み合わせることで、物理的な距離を感じさせないチーム運営が可能になります。
評価方法を見直す
従来の「勤務態度」や「上司からの印象」に依存した評価では、ハイブリッドワークの特性に合いません。そこで重要になるのが、成果やアウトプットを中心に据えた評価方法です。サイオステクノロジーの調査でも「業務状況の把握が難しい」と回答した企業は50%にのぼり、評価の見直しが急務となっています。
具体的には、目標設定を明確にし、達成度を定量的に測れる仕組みを導入することが有効です。さらに、定期的な1on1面談を行うことで、数値だけでは見えない努力や工夫も評価に反映でき、従業員の納得感を高められます。
ハイブリッドワークに関するよくある質問

ハイブリッドワークを検討している企業からよく寄せられる疑問についてまとめました。
ハイブリッドワークのうち、出社の割合は?
出社と在宅の割合は企業や業務内容によって異なりますが、一般的には「週2~3日出社」が多く採用されています。完全リモートや完全出社ではなく、チームで顔を合わせる日と個人作業に集中する日をバランスよく組み合わせる形です。
サイオステクノロジーの調査でも、企業の多くが「出社は週の半分以下」で運用していることが明らかになっています。割合を決める際は、業務の特性や従業員の希望を踏まえて柔軟に調整することが成功のポイントです。
ハイブリッドワークの導入率は?
ハイブリッドワークの導入率は調査によって異なりますが、複数の最新データからも普及が進んでいることが確認できます。たとえば、サイオステクノロジーの調査では企業全体の65%が導入済みで、大企業に限ると9割近くに達しています。一方で中堅・中小企業でも半数以上が導入しており、企業規模を問わず一般化しつつある状況です。
ただし導入が進む一方で、「コミュニケーション不足」(63%)や「業務状況の把握」(50%)など課題も指摘されています。つまり、ハイブリッドワークは単なる制度導入で終わらず、マネジメントや評価制度の見直しも含めた全社的な取り組みが求められているといえるでしょう。
中小企業でも導入できる?
ハイブリッドワークは大企業だけでなく、中小企業でも十分に導入可能です。確かにオフィススペースやIT環境の整備にコストがかかる場合もありますが、クラウド型の業務ツールを活用すれば低コストで運用できます。
また、小規模だからこそ従業員一人ひとりの意見を取り入れやすく、スピーディーに制度を改善できるメリットもあります。大切なのは「自社に合った形を見極めること」であり、必ずしも大企業と同じ仕組みを真似する必要はありません。
ハイブリッドワーク導入企業まとめ

ここまで見てきたように、ハイブリッドワークは多くの企業で導入が進み、従業員の満足度向上や採用力強化に効果を発揮しています。一方で、コミュニケーション不足や評価制度の課題も浮き彫りになっており、成功させるには全社的な工夫が不可欠です。
特に若い世代のニーズに応えるうえで、ハイブリッドワークはもはや「選択肢」ではなく「必須条件」といえるでしょう。今後も企業規模を問わず普及が進み、標準的な働き方として定着していくと考えられます。
ハイブリッドワークのペーパーレス化はMailMateで解決

ハイブリッドワークを実践するうえで意外に課題となるのが、紙の書類管理です。契約書や請求書、税務関連の書類などを紙ベースで扱っていると、在宅勤務の従業員がすぐに参照できず、承認や処理が滞ってしまいます。
また、郵送や保管のコスト、セキュリティリスクも無視できません。そこで役立つのが、クラウド型私書箱サービスの「MailMate」です。紙の郵便物や領収書などの書類をスキャンしてデータ化し、安全なオンライン環境で共有できるため、どこにいても必要な書類にアクセス可能になります。
これにより、業務のスピードアップだけでなく、セキュリティや管理面の安心感も得られる点が大きな魅力です。
クラウド郵便MailMateが、会社の郵便物の受け取り代行・スキャン・PDF化・管理画面へ配信いたします。利用開始から30日間は全額返金保証付き 🎉
郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?
クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。

