海外移住後も年金の受け取りは可能!必要な手続きをケース別に解説
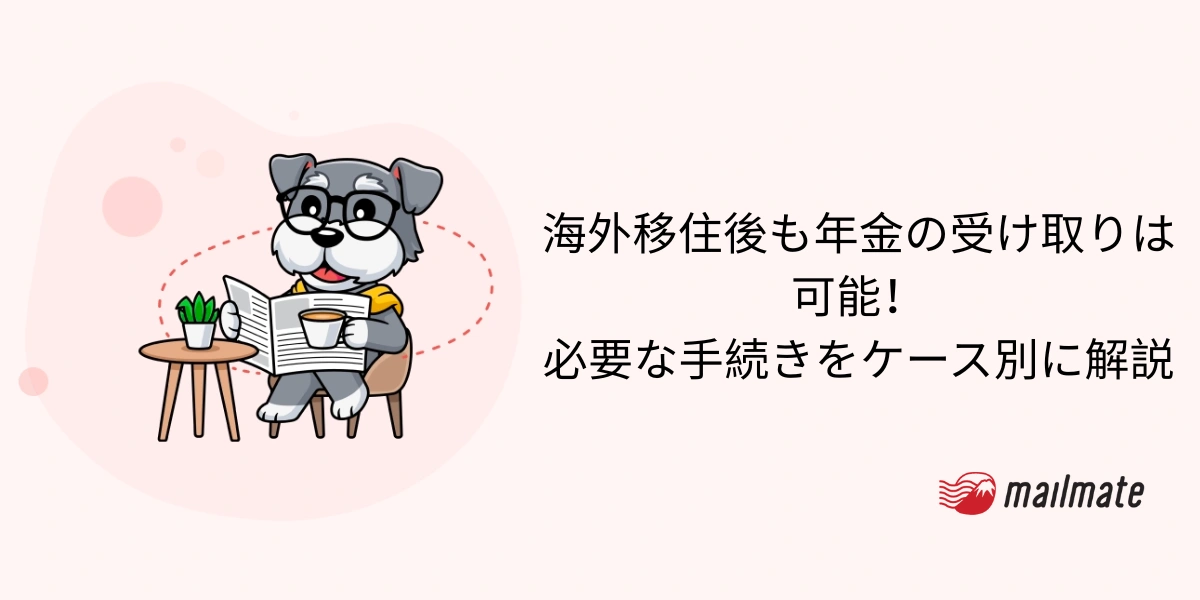
「海外移住してからも国民年金は受給できる?」
「海外移住者にも年金の支払い義務はある?」
「海外の金融機関でも年金は受け取れる?」
この記事では、こうした疑問にお答えしていきます。
日本に住んでいると、国民年金の支払い義務が発生します。一方、海外に移住すれば支払い義務はなくなるため、「海外移住後は年金を受け取れない」と思っている人も多いでしょう。
ところが海外に住んでいても、国民年金は受給できます。ただし自動で給付されるわけではないため、自分で手続きをしなければなりません。
そこで本記事では、年金の受給や支払いに必要な手続き、注意点などを解説します。海外移住を考えている方は知っておくとよいですね。
世界中どこからでも日本の住所に届く紙の郵便物をリアルタイムにパソコン・スマホ上で受け取り・管理ができます💻
日本の年金制度は「2階建て」

日本には国民皆年金の原則があり、20歳以上60歳未満の人には年金への加入が義務付けられています。加入者には保険料の支払い義務も発生し、滞納すると督促や財産差し押さえにつながることもあります。
そして日本の年金制度は「2階建て」。国民年金が1階、厚生年金が2階に当たり、それぞれ対象者や給付金額が異なります。
それぞれの違いを確認しておきましょう。
全員を対象とする「国民年金」
国民年金は、20歳以上60歳未満の国民全員が対象です。国民年金に加入していれば、65歳以降から老齢基礎年金の受給が可能。年金の繰り上げ受給や繰り下げ受給にも対応しており、ライフスタイルに合わせて調整できます。
被保険者は、第1号から第3号に分かれます。
第1号被保険者:自営業者、学生など第2・第3号に当てはまらない人
第2号被保険者:厚生年金の加入者(70歳未満の会社員や公務員)
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
第2号被保険者は、厚生年金とあわせて国民年金保険料も支払っています。そのため国民年金の保険料だけを別で支払う必要はありません。また第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者全体で支払います。
支払免除期間によって受給できる年金額は変わる
40年間未納なく保険料を支払った人は、老齢基礎年金を満額(年額816,000円)受け取ることができます。ただし保険料の支払免除期間があると、その期間に応じて受給額が減るため注意が必要です。
国民年金には学生対象の「学生納付特例制度」、所得が少ない人向けの「保険料免除制度」など、経済状況に応じて保険料の支払いを免除できる制度があります。年金の受け取り額は満額の7/8〜1/2まで減りますが、支払免除期間も年金加入期間として扱われます。
10年以内であれば追納制度も利用できるため、受給できる年金額を増やしたい人は検討してください。
会社員や公務員を対象とする「厚生年金」
厚生年金とは、国民年金にプラスして加入する年金です。事業所単位で加入し、保険料は従業員と事業所が折半で支払います。
厚生年金は会社員や公務員、あるいは次の条件に当てはまる人が対象です。
特定適用事業所や任意特定適用事業所、国や地方公共団体の事業所で働いている
週の所定労働時間が20時間以上
所定内賃金が8.8万円/月以上
学生でない
厚生年金に加入していれば、65歳以降は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受給できます。ただし標準報酬月額によって支払う保険料が異なり、その保険料に応じて給付額も変わってきます。
海外に移住したら年金はどうなる?受取・支払は可能?

滞りなく年金の支払いをしてきた人は、原則65歳から年金受給の対象となります。繰り上げ受給をすれば60歳以降に受給開始できますし、繰り下げ受給をすれば最大75歳まで受給を延長することもできますが、それによって受給できる年金額も変わるので注意しましょう。
受給対象者には、日本年金機構から年金請求書が送られてきます。それをもとに必要な手続きを行えば、年金受給を開始できますよ。
海外移住後も受給要件は変わらない
年金の受給要件には、「日本在住」という項目は含まれていません。そのため海外に移住しても、以下の要件を満たしていれば老齢基礎年金の受給が可能です。
満65歳(繰り上げ受給の場合は60歳)以上である
国民年金の資格期間が10年以上ある
資格期間とは、保険料を支払った期間と免除期間等の合算です。
なお老齢厚生年金の受給要件は、「老齢基礎年金の受給要件を満たしており、厚生年金の加入期間があること」となっています。
任意加入制度を使えば継続加入もできる
海外移住の際は、基本的に国民年金の加入資格は失われます。一方で厚生年金は住所を問わず加入できるため、適用事業所で働いている間は加入資格を持ちます。心配な人は勤務先と確認しておきましょう。
そして日本国籍を持っていれば、海外在住中も国民年金の任意加入が可能です。国民年金を継続することで、以下のメリットが得られます。
納付済期間が延び、老齢基礎年金の受給額が上がる
海外で死亡した際に遺族年金を受け取れる
海外で病気やケガによる障害が残った際に障害年金を受け取れる
任意加入する場合は、市区町村の国民年金担当窓口で手続きを行ってください。
社会保障協定を結んでいる国もある
日本は2025年10月時点で、アメリカやイギリス、中国やドイツなど23カ国と社会保障協定を結んでいます。社会保障協定の目的は、以下の2点です。
二重加入を防ぐ
年金の加入期間を通算する
たとえば移住先の国がアメリカなら、本来はアメリカの社会保障制度に加入すべきです。ところが日本企業に所属する駐在員などは、日本とアメリカそれぞれで保険料が課せられてしまい、負担が増大します。日本が社会保障協定を結ぶことで、こうした二重加入を防止できるのです。
また現地で支払った保険料を、日本の年金加入期間としてカウントできる点も大きな利点。海外移住期間があっても、年金の加入期間を満たしやすくなりますよ。
クラウド私書箱 MailMateを使うと、世界中どこからでも自宅に届く紙の郵便物をリアルタイムにパソコンやスマホ上で確認・管理できます 📩
【ケース別】海外で年金を受け取る・支払う際の手続き

年金の受給資格があっても、自動的に年金給付が始まるわけではありません。特に海外移住しながら年金を受給する場合、より手続きが複雑になってしまいます。
ここでは海外移住に伴う年金手続きについて、海外移住後に年金受給を始めるケース、年金受給中に海外移住をするケース、海外移住後も年金に任意加入するケースの3つに分けて解説していきます。
ケース1)海外移住後に年金受給を開始する場合
海外移住後に65歳を迎える人は、海外で年金請求手続きを行います。日本のように年金請求書は送付されてこないため、ホームページから年金請求書をダウンロードしておく必要があります。

引用:年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)|日本年金機構
年金請求書のほか、以下の書類も添付しましょう。受給権が発生した日以降、かつ提出日の6カ月以内に交付された書類を用意してください。
戸籍謄本や住民票など申請者の生年月日を示す書類
年金を受け取る金融機関の通帳かキャッシュカード
家族構成や加入期間によっては追加書類の提出を求められるため、事前の確認が必要です。必要書類を揃えたら、元々住んでいた地域の年金事務所、あるいは年金相談センター宛に提出します。
ケース2)すでに年金を受給している人が海外移住する場合
年金受給中に海外へ移住する場合には、日本年金機構宛に以下の書類を提出します。
外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届
(海外の金融機関を使う場合)口座証明、小切手帳や通帳のコピー
提出期限は、年金支払日を迎える前々月の末日です。スムーズに受給するためにも、早めの手続きを心がけましょう。
ケース3)海外移住後も年金に任意加入する場合
海外への移住予定者も海外在住者も、国民年金への任意加入は可能です。必要書類は「国民年金被保険者関係届出書(申出書)」。手続き窓口は市区町村の窓口か、年金事務所となります。日本に家族が残っていれば、家族が手続きしても構いません。
保険料の納付方法には、2パターンあります。
日本に住む家族等が代理で納付する
日本国内の銀行口座から引き落とす
なお任意加入の場合は、学生納付特例や免除手続きは使えないため注意してください。
参考:国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)|日本年金機構
海外移住 年金に関するQ&A
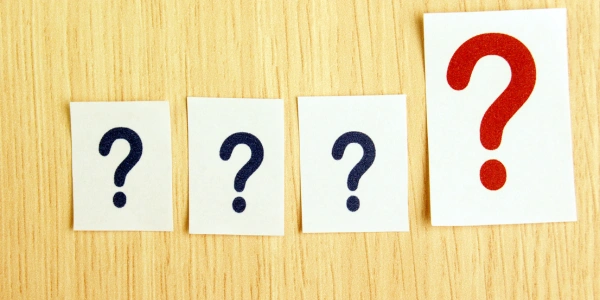
最後に、海外移住時の年金に関する質問にお答えしていきます。海外移住を考えている人や海外赴任を控えている人は、ぜひ参考にしてください。
Q1)年金受給ができない際には支払った保険料も返金される?
年金加入期間などの受給要件を満たさなければ、年金の受給はできません。支払った保険料が返金されることもないため、支払い損になってしまいます。
保険料を無駄にしたくない人は、保険料の支払いができない期間は免除制度を使う、任意加入制度を活用するなど、10年以上の加入期間を満たすようにしましょう。
Q2)国民年金を海外の口座で受け取ることは可能?
海外の金融機関の口座でも、年金受給は可能です。ただし以下の情報が必要になるので、確認しておいてください。
金融機関のSWIFT(BIC)コード、都市名
受取人が住む州名、都市名 など
あわせて口座証明や小切手帳のコピー、通帳のコピーなどの添付も求められます。
Q3)年金の請求手続きを行うタイミングはいつ?
年金の受給開始年齢は65歳ですが、受給権が発生するのはその前日です。つまり8月1日に65歳になる場合、7月31日に年金の受給権が発生します。
そして請求手続きを行うのは、受給権が発生した日以降です。たとえば先の例では、7月31日から年金請求手続きができるようになります。提出が遅れても通常はさかのぼって年金を受給できますが、5年を経過すると時効になり、権利が消滅してしまうため注意しましょう。
海外生活を安心して送るためにも年金制度を利用しよう
本記事では、海外移住者が知っておくべき年金手続きについて解説しました。海外移住後も年金の受給・支払いは可能なので、必要な手続きを行って、老後の安心材料として活用できるとよいですね。
ただ、海外では日本に届く郵便物が受け取れません。家族に代理受け取りを頼む方法もありますが、自分で郵便物を管理したい人には、クラウド私書箱・メールメイトがおすすめです。

メールメイトは紙の郵便物をPDF化し、データとしてアップロードしてくれます。海外からも郵便物の確認ができますし、重要な郵便物を見逃す心配がなくなりますよ。請求書の支払い代行も可能なので、いざという時もお任せできます。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
クラウド私書箱メールメイトを使うと、世界中どこからでも自宅に届く紙の郵便物をパソコンやスマホ上で確認・管理できます 📩
おすすめ記事:
郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?
クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。

