受け取りたくない郵便物の受け取りを拒否する方法と注意点を解説
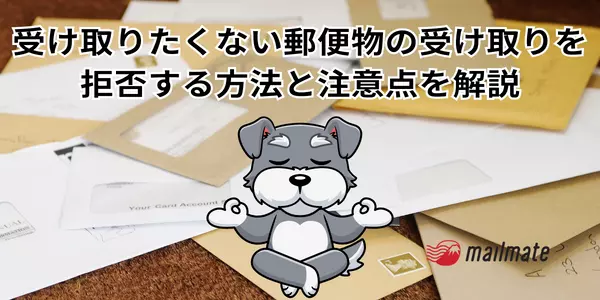
「郵便物の受け取りを拒否する方法が知りたい!」
「受取拒否したことは相手にわかるの?」
こんな悩みや疑問を抱えている方はいるでしょうか。
しつこいダイレクトメールや差出人不明の郵便など、受け取りたくないものが配達された場合、開封せずに「受取拒否」をすることができます。
ただ郵便物受け取り拒否の方法や注意点については、知らない方も多いでしょう。
そこで今回は郵便物を受取拒否する方法や、その際の注意点を解説します。
受取拒否に関するさまざまな疑問にも答えていくので、参考にしてくださいね。
メールメイトなら届いた瞬間にスキャンされ、不要な郵便はワンクリックで処理できます。自宅の住所を公開せずに郵便を受け取れるのも安心。
迷惑な郵便物の種類はさまざま
毎日さまざまな郵便が届くなかで、時には「迷惑」と感じるものもあるでしょう。
あるいは「心当たりがない」「差出人がなくて怖い」感じた経験のある方もいるかもしれません。
ダイレクトメール
カタログやパンフレット
差出人不明のもの
いたずらや詐欺目的の郵便
このほか、2020年には覚えのない種が送られてくる事件も頻発していました。
このような迷惑な郵便が届いたら、多くの方は部屋に持ち帰ったうえで廃棄するでしょう。
ただ1度や2度ならそれでよくても、それが何度も続くと嫌になる方もいるかもしれません。
そういう時に役立つのが「郵便物の受取拒否」というシステムです。
郵便物の受け取りを拒否する4ステップ
郵便は、ポストに投函された時点では受け取ったことになりません。
封筒を開けてはじめて「受け取った」とみなされるのです。
そのためポストに投函された郵便であっても、受取拒否をすることはできます。
もしも迷惑な郵便が届いてしまったら、開封する前に受取拒否をしましょう。
1. メモ用紙か付箋を用意する

2. その紙に「受取拒絶」と書き、署名または捺印する

3. 2の紙を封筒に貼り付ける

4. 3の封筒を郵便局に持参するか、ポストに投函する

参考:日本郵便HP
メモ用紙や付箋に書く代わりに、「受取拒絶」と書かれたスタンプを押してもよいでしょう。
封筒に直接書いても問題ありません。
一般的な郵便を受取拒否する場合はフルネームでの署名か捺印が必要なので、忘れないようにしてください。
メールメイトなら、届いた郵便をオンラインで確認・整理。不要な郵便物はダッシュボードから即破棄できます。
おすすめ記事:【本人限定受取郵便】心当たりない…何が届く?受け取り方も解説
はがきやゆうパックなども同様に対応できる
日本郵便のサービスであれば、上記の方法で受取拒否ができます。
つまり以下であっても、同じように対応できるのです。
ただし例外として、裁判等で使われる「特別送達」に関しては受取拒否ができません。
配達員がその場に置いて帰る差し置き送達が認められているうえ、受取拒否したことで裁判の際に不利になってしまいます。
日常ではほとんど見かけませんが、万が一「特別送達」が届いた場合は、きちんと受け取るようにしてください。
受け取りを拒否できない郵便物もある
郵便物の受取拒否は簡単にできますが、注意点もあります。
場合によっては受取拒否ができなくなってしまうので、しっかり確認しておきましょう。
受取拒否できる郵便物は「未開封」に限る

いったん封筒を開けたものは、受取拒否ができません。
それ以外にも下記に当てはまる場合は、いずれも「開封した」とみなされるため、受取拒否ができなくなります。
サインをして受け取った
料金を支払った
付いているシールをはがした
書留やゆうパックなど、配達員から直接受け取るものは、サインをする前に配達員へ受取拒否したい旨を伝えてください。
着払いの郵便も料金を支払ったあとでは受取拒否ができないので、心当たりがない場合は料金を支払う前に確認することをおすすめします。
はがきについては封を開ける必要がないため、読んだ後でも受取拒否ができます。ただし圧着部分をはがした後は受取拒否できないので、注意してください。
郵便物以外の受取拒否はできない

日本郵便のサービスであれば、特別送達を除いて受取拒否が可能です。
ただ佐川急便やクロネコヤマトのサービスなど、「これは郵便物ではありません」「○○メール便」などの表記があるものは対応が異なります。
飛脚メール便(佐川急便)
クロネコDM便(クロネコヤマト)
Amazonの商品(商品によって配送方法が異なる)
上記は一例ですが、このようなサービスで受取拒否をする場合は、配送業者に連絡しましょう。
事前に配送がわかっていれば電話で伝えても良いですし、配達時に配達員に直接伝えることも可能です。
こちらも開封済のものは受取拒否できないので、注意してください。
開封してしまった場合の対処法

郵便物を開封してしまった場合は受取拒否ができないので、速やかに差出人に直接連絡し、送付の停止を明確に伝えましょう。
メールでその旨を伝えることで証拠として残るので、後々トラブルになった時に有効です。
しつこい営業郵便の場合は消費者センターへ相談するか、特定商取引法に基づく送付停止要求をしましょう。
悪質な場合は、迷惑行為として警察へ相談するのが良いでしょう。
間違って重要書類を拒否してしまった場合の対処法

重要書類を間違えて拒否してしまった場合は以下の対応を行いましょう。
差出人に連絡:事情を説明・謝罪し、再送を依頼する
郵便局に相談:まだ返送途中の場合は止められる可能性があるので、その際は受取拒否の撤回を申し出る
法的な期限がある場合は弁護士に相談
特別な郵便物に注意

受取拒否をする際に注意したいのが、「内容証明郵便」や「配達証明付き郵便物」など、法的効力がある郵便物です。
これらの郵便物は、発送元が 「いつ・誰に・どのような内容を送ったのか」
を証明するために送ってくるもので、重要な通知や請求、契約書などが含まれていることが多いです。
受け取りを拒否してしまうと、相手側に「通知が届いた」と認められてしまい、後々トラブルの原因になることがあります。例えば、契約に関する内容証明郵便を拒否して返送した場合、裁判所や相手方が「通知された」として不利な立場に立たされることもあります。
そして、内容証明郵便が返送されると、相手が次にどのような手続きを取るかによって、思わぬ負担や責任を負う可能性も出てきます。
そのため、こういった郵便物は、受取拒否をする前に一度中身や発送元を確認して、必要であれば弁護士や専門家に相談することをおすすめします。
注意深く対応することが大切です。
受け取り拒否で注意すべき郵便物の種類
上記を踏まえて、絶対に受取拒否をしてはいけない郵便物と慎重に受取拒否の判断をすべきものを紹介します。
絶対に受取拒否してはいけないもの
裁判所からの特別送達(「特別送達」の赤いスタンプ)
内容証明郵便(「内容証明」の表記)
配達証明付き郵便物
行政機関からの通知
慎重に受取拒否の判断をするべきもの
税務署、年金事務所からの郵便
医療機関からの検査結果
金融機関からの重要書類
賃貸契約に関する書類
関連記事:法律事務所や弁護士から郵便物が届いたら?無視のリスクと家族にバレない対策を解説
郵便受け取り拒否に関するQ&A

ここからは郵便物の受取拒否に関して、気になる疑問点を一つずつ回答していきます。
Q.受取拒否した郵便物はどうなる?
A.差出人に返送、あるいは郵便局に保管されます。
差出人が書いてある郵便を受取拒否した場合は、差出人の元へ返送となります。
一方で差出人が不明の郵便は、以下の流れで処理されます。
郵便局にて郵便物を開封する(→差出人がわかれば返送する)
差出人がわからなければ、3ヵ月間は郵便局で保管される
3ヵ月経っても差出人が現れなければ、郵便局で破棄される
Q.郵便物の受取拒否に費用はかかる?
A.受取拒否することでかかる費用はありません。
郵便物を受取拒否すると差出人へ返送されるため、その分の切手が必要かと考える方もいるかもしれません。切手代や手数料などの費用を請求されることはないので、安心してください。
差出人側としても、最初の切手代は必要ですが、追加でかかる費用はありません。
Q.受取拒否したことは相手にわかる?
A.「受取拒絶」の文字が残った状態で返送されるため、相手にわかります。
受取拒否をする際は、メモ帳や付箋に「受取拒絶」の文字と署名を記して封筒に貼ります。実はこの紙は、郵便局員によってはがされることはありません。
署名も残った状態で差出人の元に届くため、誰が受取拒否したのか明確にわかるシステムなのです。
Q.受取拒否した郵便物は二度と届かない?
A.差出人によって対応は異なりますが、届かないケースが多いでしょう。
一般的な会社であれば、ダイレクトメールの送付リストから外すなどの対応をとるはずです。
ただし郵便物の受取拒否は、「受け取りたくない」という意思を示すもので、「送ってはいけない」などの強制力はありません。
そのため差出人によっては、ふたたび郵便を送ってくる可能性があります。
その場合はふたたび受取拒否をするか、差出人に直接連絡するなどの方法をとる方がよいでしょう。
オンラインで郵便物が受け取れるサービスもある
ここまで迷惑な郵便物の受け取りを拒否する方法や、その注意点について解説しました。
受取拒否には手間も費用もかからないので、しつこいダイレクトメールに困っている方は試してみるとよいでしょう。
また、迷惑な郵便が家に届かないようにする方法として、オンラインで郵便が受け取れるクラウド郵便サービスもおすすめです。

MailMateもその一つで、オンラインで郵便の受け取りや開封、保管ができます。
ダッシュボード上でいらない郵便の破棄を選択すると原本を破棄することもできます。
いちいち封筒を開く手間が省け、メールのように確認できるのもポイントです。
MailMateの主な機能
MailMateには、郵便物の管理に役立つ機能が多く搭載されています。
郵便物の受け取り&未開封スキャン
郵便物の開封&内容スキャン
スキャンデータのクラウド保管
郵便物の転送
郵便物の到着通知
請求書の支払い代行
メールメイトの住所に届いた郵便物は、スキャンされてクラウド上に保管されます。そのためインターネット環境さえあれば、どこからでも郵便物の確認が可能。データとして管理できるので、保管に手間がかからず、共有がしやすいのもポイントです。
メールメイトご利用の流れ
STEP 1: 無料アカウント作成でダッシュボードを見てみる
まずは、無料アカウントを作成して、実際にメールメイトの郵便物管理ページ(ダッシュボード)を見てみましょう。実際にサービスの利用をご検討する場合、ダッシュボード内からデモを予約いただけます。
STEP 2: ご本人様確認後、転送届の手続き
Web会議ツールを使いデモ(使い方に関する説明等)
プラン選択
電子契約書に署名(秘密保持契約書、委任状、同意書)
転居届の提出
転送が開始されるとオンライン上で郵便物の受け取りが可能に。
STEP 3: パソコンやスマホから郵便物を確認・管理
郵便物がアップロードされると通知が届きます。Web上のメールメイトダッシュボードより郵便物の開封、スキャン、転送、破棄、そして請求書の支払い代行の依頼が可能です。
メールメイトの料金プラン

MailMateではご利用の目的別に様々な料金プランがあります。年間契約で月額20%割引になり、個人向けなら月額1500円〜利用できます。
郵便の多いフリーランサーや出張が多くて郵便の受け取りが難しい方、同居人と郵便物を分けて受け取りたい方などにもおすすめですよ。
料金は月額1500円〜で、30日間は返金保証もついているので安心してお試しいただけます。
まずは無料でアカウントを作成してみてはいかがでしょうか?
サービスの詳細が気になる方はMailMate公式サイトをご覧ください。
クラウド郵便のMailMateがお客様の郵便物を受け取り代行・スキャン・PDF化いたします。自宅宛の郵便物をパソコンやスマホ上で管理🛡
【関連記事】
郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?
クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。

