個人事業主は事務所なしでも大丈夫?メリット・デメリットを解説
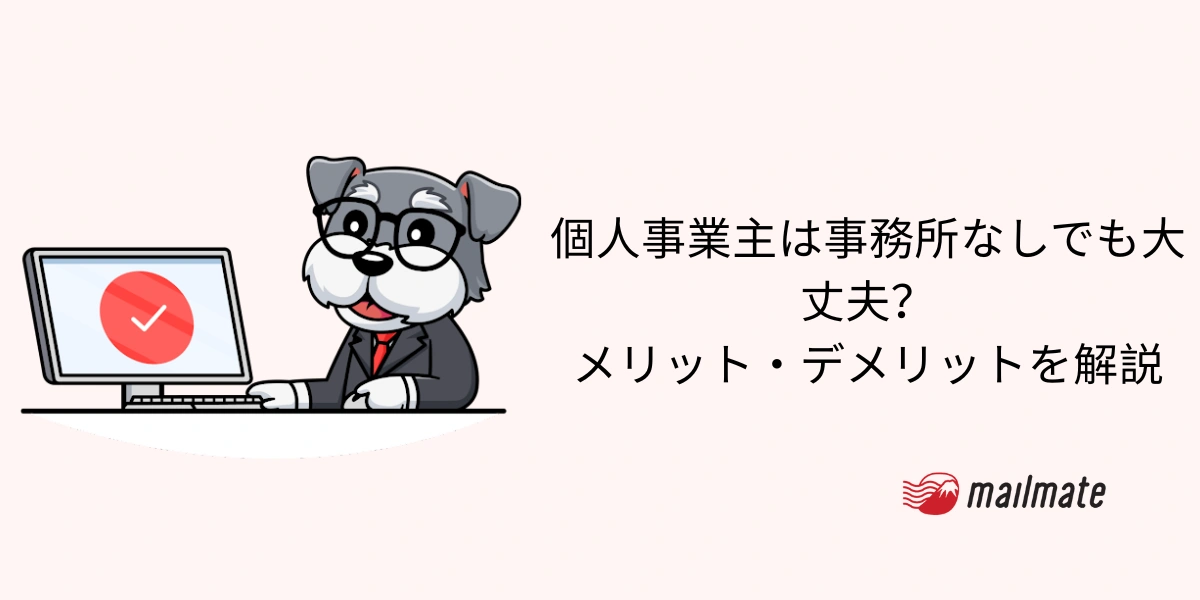
「個人事業主には事務所なしの状態でもなれる?」
「自宅で仕事をしているけれど、なるべく住所は公開したくない」
「個人事業主が自宅以外の住所を使うことはできるの?」
この記事では、こんな疑問や悩みを解決していきます。
近年では働き方が多様化し、自宅で仕事をする人も増えてきました。自宅で仕事ができれば事務所を借りる必要はありませんが、一方で取引先に自宅の住所を教えるのは抵抗がある、かといって事務所を借りる余裕はないなど、悩んでいる個人事業主も多いでしょう。
そこで本記事では、個人事業主が事務所を持たないメリット・デメリットについて解説します。自宅以外の住所を使う方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
メールメイトは、会社宛の郵便物を全てデジタル化する新しいバーチャルオフィスです。福岡市/京都市/東京都港区・新宿区の住所を提供しています。
そもそも個人事業主とは

個人事業主とは税法上の呼び名で、法人化をしないまま継続的・反復的に事業を行っている人のことです。たとえ従業員を雇っていても、法人化していなければ個人事業主として扱われます。
個人事業主になるには、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」、つまり開業届の提出が必要です。事業開始から1ヶ月以内に提出してください。
開業届には納税地を記載する欄があるので、自宅や事務所の住所を記載します。納税地の変更をする場合には、変更の届出が必要となります。
フリーランスとの違い
フリーランスとは働き方の呼び名であり、税法上の定義はありません。厚生労働省の定義は「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長」であり、自分の経験やスキルをもとに収入を得ている人を指します。
個人事業主でありながら、フリーランスという働き方をしている人も多いです。開業届を出すかどうかは個人の判断なので、届出をせずにフリーランスとして働き続ける方法もありますよ。
ただ開業届を提出して個人事業主になれば、確定申告の際に青色申告特別控除が受けられます。所得税や住民税の節税になるので、知っておくとよいでしょう。
参考:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要)
個人事業主が自宅を事務所にする場合のメリット

個人事業主のなかには自宅で仕事をしている人、つまり自宅を事務所利用している人も多いです。たとえばWebデザイナーやWebライター、プログラマーやエンジニアなどは、パソコンさえあればどこでも仕事ができるため、自宅兼事務所でも働きやすい業種といえます。
自宅を事務所にするメリットは、大きく2点挙げられます。
メリット1)コストを抑えられる
最大のメリットは、コストを抑えられる点。オフィスを借りるには敷金や礼金、内装費などが必要です。起業したてで予算がない時期だと、大きな負担となることもあるでしょう。
自宅兼事務所の場合は、そうしたコストがかかりません。家賃や水道光熱費などのランニングコストもかからないうえ、一定割合は経費として計上することも可能です。コストを大きく抑えられるでしょう。
メリット2)通勤時間がかからない
通勤時間がかからない点も、大きなメリットです。通勤にかかっていた時間を別のことに充てられますし、満員電車などのストレスも軽減されます。
これはリモートワークのメリットとしてもよく指摘される点です。厚生労働省の調査によると、会社員の62.3%が「通勤に費やしている時間を有効に使える」という点をよい影響として感じているそうです。
個人事業主が自宅を事務所にする場合のデメリット

自宅を事務所にするメリットは大きいものの、そこにはデメリットも存在します。ここでは3点ご紹介するので、順に確認していきましょう。
デメリット1)公私が混ざりやすい
本来なら事務所は「公」の空間ですし、自宅は「私」の空間です。事務所では集中して仕事をして、その後は自宅でゆっくりくつろぎたいですよね。
ところが自宅兼事務所の状態では、公私の区別が付きにくくなってしまいます。仕事中に家族から声がかかって集中力が途切れることもあれば、つい趣味のものに意識が向いて仕事に集中できないこともあるでしょう。反対にいつまでも仕事が止められず、プライベートが犠牲になりがちな人もいます。
自宅兼事務所にする場合は、いかに公私を切り替え、生活にメリハリを付けるかが課題となります。
デメリット2)プライバシー面に不安が残る
個人事業主として仕事をしていると、どこかで住所を伝える機会があるでしょう。契約書や請求書に住所を記載することも多いですし、年賀状など郵便物のやり取りをするかもしれません。
そのため自宅兼事務所にしている場合、取引先には自宅の住所を伝える必要があります。ただし取引先とはいえ、自宅を明かすことに抵抗を感じる人もいるはず。プライバシー面でも不安が残ります。
また将来的に法人化した場合、登録した登記住所はインターネット上で公開されます。法人化する予定のある人は、自宅とは別に事務所を持つことも検討するとよいでしょう。
関連記事:個人事業主の住所がバレるのを防ぎたい!できる対策を詳しく紹介
デメリット3)取引先からの信用を得にくい
自宅とは別に事務所を持っていると、相手に「信頼できる会社だ」「それなりに資金力もあるようだ」という印象を与えます。反対に自宅兼事務所にしていると、「審査に通らないのか」「事務所を用意する資金がないのか」と捉えられる可能性があるのです。
取引先によっては、自宅兼事務所にしていることで信用を得にくくなるかもしれません。
賃貸物件は大家さんや管理会社への相談が必須
賃貸物件を事務所にする場合は、1つ注意点があります。それは、賃貸物件のなかには居住用の賃貸物件・事業用の賃貸物件の2つがあること。両者には契約期間や敷金や保証金の額など、さまざまな違いがあります。
賃貸物件のほとんどは居住用です。居住のために借りた物件で事業を始めるには、事前に賃貸借契約や規約を確認し、大家さんか管理会社に許可をとらなければなりません。事業内容によっては許可が下りることもありますが、来客が多い職種などは許可が下りない可能性もあります。
また看板を出す、広告を貼るといった行為も、許可なく行わないように注意してください。
個人事業主の住所を自宅以外に置くことも可能

「プライバシーを守りたい」「住んでいるのが賃貸物件で事業用住所として登録できない」などの理由から、自宅以外の住所を持ちたいと考える個人事業主もいるでしょう。実は自宅以外の住所を納税地として登録することや、法人口座開設用の住所として登録することも可能です。
ここでは、個人事業主が自宅以外の住所を持つメリット・デメリットを考えてみましょう。
大きなメリットはプライバシーが守られる点
事業用として自宅以外の住所を持つことができれば、仕事関係者に自宅の住所を伝える必要はなくなります。将来的に法人化した場合も、自宅以外の住所で登記を行えば良いので、プライバシーを守りやすくなるでしょう。
また住所によっては、社会的信用が高まる点もメリットの一つ。たとえばオフィスの住所が都心の一等地なら、信頼できる会社という印象が付きますよね。実際に「住所が決め手となって契約が取れた」という個人事業主もいます。
コストがかかる点はデメリット
自宅以外の住所を持つには、それなりにコストがかかります。比較的手ごろな料金のバーチャルオフィスでも、月々千円〜1万円ほど必要です。
さらに自宅外のオフィスに通うのであれば、そこまでの交通費もプラスされます。予定外の出費に慌てることのないよう、あらかじめ予算を立てておくと安心です。
個人事業主が自宅以外の住所を利用する3つの方法

個人事業主が自宅以外の住所を利用するには、3つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分のワークスタイルや予算に合わせて、適するものを選びましょう。
①バーチャルオフィス|自宅で仕事をしたい方におすすめ
メリット:低コストで一等地の住所が使える
デメリット:実際の仕事場は借りられない
バーチャルオフィスは実際の仕事場ではなく、仕事用の住所をレンタルするサービスです。月々千円~1万円という低コストで利用できるうえ、サービスによっては一等地の住所を借りられる点も大きなメリット。法人登記に使えるサービスも多いので、法人化した後も安心です。
ただし住所のみのレンタルなので、来客対応には向きません。なかには会議室が借りられるサービスもありますが、予約が埋まっていると使えないので注意が必要です。
メールメイトは、会社宛の郵便物を全てデジタル化する新しいバーチャルオフィスです。福岡市/京都市/東京都港区・新宿区の住所を提供しています。5年間営業保証も付いています🛡
②レンタルオフィス|すぐに使いたい方・短期利用したい方向け
メリット:初期投資を抑えて仕事場が借りられる
デメリット:長期利用にはコストパフォーマンスが悪い
レンタルオフィスとは、個室に机やイス、インターネット環境などが揃っており、共有スペースにはコピー機などのオフィス家具がある施設のこと。ユーザーは個室で仕事をしながら、共有スペースも自由に利用できます。
自分で内装を整える必要がないうえ、敷金・礼金も不要です。賃貸オフィスより初期投資を抑えられて、契約後はすぐ入居できます。
一方で月額料金は、数万円〜10万円ほどとやや高額。短期利用には向いていますが、長期利用するにはコストパフォーマンスが悪いといえます。
③賃貸オフィス|自分だけのスペースなので自由度が高い
メリット:広く使えるので人を招きやすい
デメリット:初期費用・ランニングコスト共に高い
賃貸オフィスとは、賃貸住宅と同じように不動産契約を結んでオフィスを借りることを指します。工事をするには大家さんの許可が必要ですが、レイアウトや内装は自由に変えられるうえ、広く使えるのがメリット。自分だけのスペースなので、来客の多い業種でも安心です。
もちろんその分コストは高くなり、目安は坪単価で1万円〜2万円ほど。さらに水道光熱費や内装費、敷金・礼金も加わるため、まとまった料金が必要です。
そのため起業したてではなく、事業が軌道に乗ってから検討してもよいでしょう。
個人事業主が事務所なしで起業する際のQ&A

最後に、個人事業主が事務所なしで起業する際の気になる疑問を解決していきます。
Q1)開業届に書いた自宅の住所は公開される?
開業届に書いた住所は、公開されることはありません。自宅の住所を書いたとしても、誰かに知られる心配は不要です。
ただしネットショップなどを運営する場合は、特定商取引法によって住所の公開が義務付けられています。自宅の住所も公開しなければならないので、注意してください。
Q2)個人事業主の自宅兼事務所で経費になるものは何?
個人事業主の自宅が事務所兼用となった場合、事業に必要な費用は経費として扱うことができます。
住宅費、固定資産税
駐車場代
通信費(Wi-Fi料金、回線料金など)
水道光熱費
消耗品費(文房具、用紙代) など
ただし住宅費や駐車場など私的利用と兼用するものは、全額が経費になるわけではありません。事業割合に応じて計算した分のみ、経費として計上できます。
Q3)自分に合ったオフィス形態がわからない!
オフィス形態によって、向いているタイプは異なります。以下に例を挙げるので、参考にしてください。
自宅兼事務所:できるだけコストを抑えたい人、公私の区別が付けられる人
バーチャルオフィス:プライバシーを守りたい人、来客の少ない人
レンタルオフィス:自宅以外で仕事をしたい人、すぐに事業を開始したい人
賃貸オフィス:来客が多い人、許認可の必要な事業(人材派遣業、探偵業など)を行う人
自分の働き方に合ったオフィス形態を選びましょう。
個人事業主は自宅兼事務所でもOKだがプライバシーは大事にしよう
本記事では、個人事業主が事務所なしで仕事をするメリット・デメリット、自宅以外に住所を持つ方法について解説しました。自宅で仕事をするメリットは大きいですが、プライバシー面が少し心配。反対に自宅外で仕事をする場合、高いコストがかかるというデメリットがあります。
そんな時は、自宅で仕事をしながらバーチャルオフィスを利用してもよいでしょう。かかるコストが少ないうえに、自宅の住所を使わずに済むため安心感が高い方法です。
ぜひ利便性・安全性の両方に納得できる形を見つけてください。
バーチャルオフィスなら郵便物管理もしやすいメールメイトがおすすめ

メールメイトは、郵便物の管理がしやすいバーチャルオフィスです。メールメイトの住所宛に届いた郵便物は、PDF化されてユーザーのマイページにアップロードされます。どこからでも郵便物の確認ができるうえ、受け取りまでにタイムラグが発生することもありません。
さらに法人口座の開設や、法人登記用の住所としても利用できます。東京都港区や新宿区など、一等地の住所が使えますよ。ぜひ1度お試しください。
メールメイトは、会社宛の郵便物を全てデジタル化する新しいバーチャルオフィスです。福岡市/京都市/東京都港区・新宿区の住所を提供しています。
郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?
クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。

