児童手当は海外赴任中も受給できる?手続き方法や注意点を解説
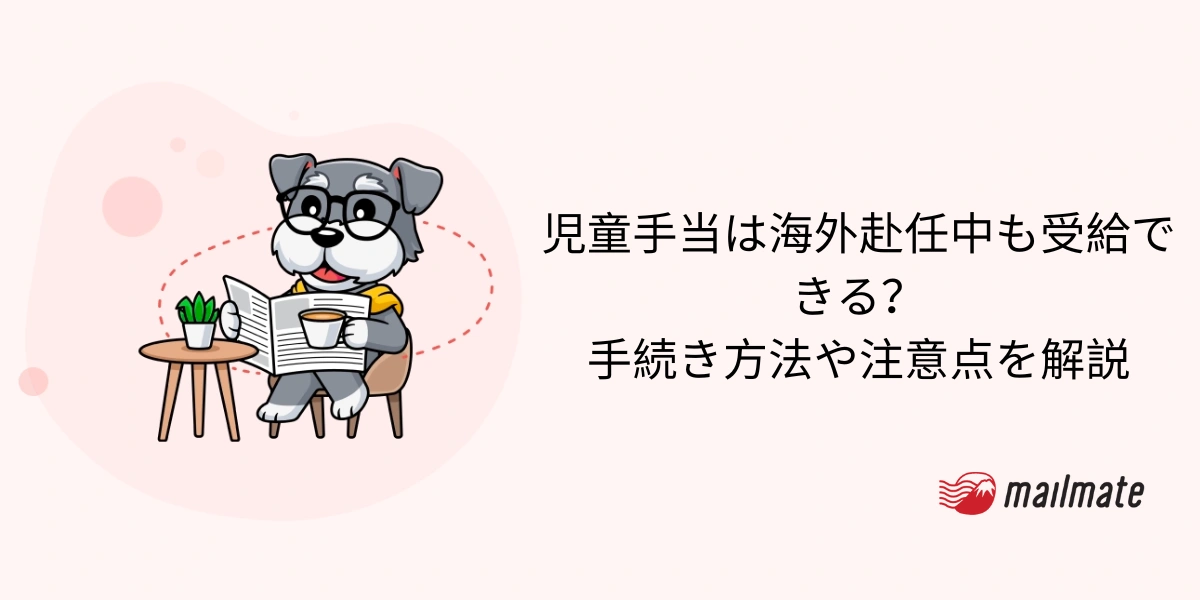
「児童手当の受給者が海外赴任になったらどうすればいい?」
「子どもが海外留学する場合も児童手当は支給されるの?」
「帰国後に児童手当を受け取るための手続きが知りたい」
本記事では、こんな疑問に答えていきます。
日本では、0歳から18歳の子どもを育てている家庭に児童手当が支給されます。ただし自動的に支給が開始されるわけではなく、市区町村への申請手続きを行って、認定を受けなければなりません。
なかには海外赴任などで日本を離れる場合など、受給が継続できなくなるケースもあります。そこでこの記事では、海外にいても児童手当を受給できるケースや、その際の手続きについて詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。
世界中どこからでも日本の住所に届く紙の郵便物をリアルタイムにパソコン・スマホ上で受け取り・管理ができます💻
児童手当制度とは?

児童手当とは、国による子育て支援制度の一つです。支給対象となるのは、0歳〜18歳の子どもを養育している人。子どもが児童養護施設や里親の元にいる場合は、両親に代わって施設の設置者や里親が受給します。
いずれの場合も、子どもが日本国内に住所を有していることが条件です。
児童手当の支給額は年齢によって変わる
児童手当の支給額は、年齢によって異なります。
0歳~3歳未満:15,000円/月
3歳~18歳の誕生日以降 最初の3月31日まで:10,000円/月
上記は第1子・第2子の場合で、第3子以降は一律30,000円/月となります。以前は所得に応じて受給できる金額が異なりましたが、2024年10月以降は受給における所得制限がなくなり、全家庭が同じ額を受給できるようになりました。
また児童手当は、偶数月に2カ月分ずつ支給される仕組みです。たとえば2月には12月分と1月分が、4月には2月分と3月分が支給されます。毎月支給されるわけではないので、ご注意ください。
児童手当を受け取るまでの流れ
児童手当を受け取るためには、住んでいる市区町村にて申請手続きを行います。受給までの基本的な流れは、以下のとおりです。
出生日から15日以内に児童手当認定請求書を提出する
書類に問題がなければ認定通知書が届く
申請月の翌月分から児童手当が支給される
スムーズに児童手当を受け取るためには、出生後なるべく早いタイミングで認定請求書を提出してください。里帰り出産をする場合も、実際に住んでいる市区町村での手続きが必要です。
申請手続きを行う際は、受給予定者のマイナンバーカードや銀行口座番号が分かる書類もあわせて持参しましょう。人によっては追加書類が必要な場合もあるので、詳しくは自治体にお問い合わせください。
公務員は勤務先で手続きを行うので注意
受給者が公務員の場合は、児童手当の支給元が市区町村ではなく勤務先となります。そのため市区町村の役所ではなく、勤務先にて申請手続きを行ってください。
また公務員を退職する場合は、支給元が市区町村に変わります。退職後も引き続き児童手当を受給するには、公務員でなくなった翌日から15日以内に市区町村で手続きを行いましょう。
児童手当は父と母のどちらに支給するか
児童手当を受け取れるのは子どもの養育者1人、つまり基本的には父か母のどちらかです。両親が子どもと同居している場合は、父母のうち所得が高いほうに支給されます。
そして児童手当の振込先は、原則として受給者名義の口座です。子ども名義の口座や配偶者の口座には支給できませんので、ご注意ください。
ただし離婚、あるいは離婚協議中などの理由で両親が別居している場合は、子どもと同居中の親に対して児童手当が支給されます。仮に両親が同意していても、子どもと別居している親が受給することはできません。
なお離婚協議中の場合は、調停不成立証明書や離婚裁判に関する控訴上の副本など、事実を確認するための書類提出が求められます。
参考:児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)|こども家庭庁
他の市区町村へ引っ越す場合は手続きが必要
児童手当は、現在住んでいる市区町村から支給されます。そのため他の市区町村へ引っ越す場合は、引き続き児童手当を受給するための手続きをしなければなりません。
手続きの流れは次のとおりです。
(前住所にて)役所に児童手当受給事由消滅届を提出する
(同)所得課税証明書を発行してもらう
(新住所にて)必要書類を揃え、役所に児童手当認定請求書を提出する
まずは前住所で児童手当の受給を停止してから、引っ越し先の市区町村で受給申請をし直します。転出予定日の翌日から15日以内に行いましょう。
ただし配偶者からのDVで避難している場合は、住民票の異動なしで受給することも可能です。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
クラウド私書箱メールメイトを使うと、世界中どこからでも自宅に届く紙の郵便物をパソコンやスマホ上で確認・管理できます 📩
海外在住中に児童手当を受給できるケース

児童手当は住民票の住所を元に支給される、日本国内に住んでいる人向けの制度です。海外転出者は日本国内に住所を持たないので、児童手当を受け取ることはできなくなります。
そのため「これまで児童手当を受給していた父が海外赴任になったから、もう児童手当は受けられない」と考える人もいるでしょう。実際に家族の誰かが海外赴任となり、家族帯同で海外に移住する場合などは、児童手当の受給を継続することはできません。
一方で、なかには海外移住後も児童手当の受給を継続できるケースもあります。ここでは主な2つのケースをご紹介するので、自分の状況が当てはまるか確認しておきましょう。
ケース1)子どもが日本に残る場合
たとえば児童手当の受給者が父という状況で、父が海外赴任になったケースを考えてみます。この時、家族そろって海外に移住するのであれば、児童手当の支給対象にはなりません。海外転出すると同時に児童手当の支給も終了します。
ところが父が海外赴任になっても、子どもが日本に残り、その養育者として母が子どもと同居を続けるのであれば、父に代わって母が児童手当を受給することができます。父母が海外転出して子どもと祖父母が同居するケースでも、祖父母が児童手当の支給対象となります。
いずれにせよ受給者の変更がある場合は、役所で受給者変更手続きを行う必要があります。父が海外転出する前に、忘れずに行いましょう。
ケース2)子どもが海外留学する場合
子どもが海外留学する場合も、児童手当の受給が可能です。ただし条件が3つあるので、以下のすべてを満たしていることを確認してください。
日本国内に住所を有しなくなった日までに、3年以上日本に住んでいた
教育を受けることを目的に海外に住むのであり、父母とは同居しない
日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内である
つまり日本に3年以上住んでいた子どもが留学した場合、かつ留学から3年以上経っていない場合は、児童手当の支給対象となります。
なお短期留学中で日本に一時帰国している場合などは、1つめの要件を満たしていなくても児童手当が支給される場合があります。
児童手当の受給者を変更する方法

父から母へ、あるいは父から祖母へなど、児童手当の受給者を変更するには、市区町村にて変更手続きを行わなければなりません。手続きの流れは、まず現在の受給者への支給を止めること、そして新しく受給者となる人が申請を行うこと。現受給者が海外転出してしまう前に、余裕を持って手続きを済ませておきましょう。
順に解説します。
ステップ1)現在の受給者に対する支給を停止する
子どもの有無に関わらず、海外転出する人は役所に海外転出届を提出しなければなりません。自治体によってはオンライン提出ができるところもありますが、窓口での提出や郵送が必要なところもあります。転出予定日の14日前〜当日までに手続きを完了させてください。
そのうえですでに児童手当を受給している方は、児童手当受給資格(受給事由)消滅届を提出し、支給を停止する必要があります。ただし「海外転出届を出していれば受給資格消滅届の提出は不要」とする自治体もあるため、事前に確認しておきましょう。
受給資格消滅届の提出方法は、窓口・郵送・オンラインの3つです。自治体によって異なる場合もあるため、注意してくださいね。
ステップ2)新しい受給者が児童手当の申請を行う
ステップ1が完了したら、新たに児童手当を受給する方が申請を行います。必要な書類には以下があります。
児童手当認定請求書
受給予定者のマイナンバーカード(または健康保険の資格証明書など)
受給予定者の銀行口座番号が分かる書類
申請内容に問題がなければ、申請日の翌月から児童手当の支給が開始されます。そのため受給者の海外赴任が決まったら、なるべく早めに手続きを済ませておくとよいでしょう。ステップ1と同じタイミングで手続きすることも可能です。
児童手当を海外から帰国後に受給する方法

家族帯同で海外赴任する場合など、誰も日本に残っていなければ児童手当の受給はできません。ただ、帰国後に必要な手続きを行えば、再度児童手当を受給することが可能です。
ここでは海外から帰国した後に、改めて児童手当を受給する際の手続きをご紹介します。
転入届と認定請求書の提出が必要
出国時は役所に海外転出届を提出しますが、帰国時は転入届の提出が必要です。郵送手続きは不可なので、必ず役所の窓口で手続きを行ってください。
さらに児童手当の申請を行うためには、児童手当認定請求書を提出しましょう。転入届と認定請求書を同じタイミングで提出することも可能です。
また手続きに当たっては、以下の書類が必要です。
児童手当認定請求書
受給予定者の健康保険証(または年金加入証明書)
本人確認書類
印鑑
個性謄本 など
自治体によっても異なるので、事前に確認のうえ準備しておきましょう。
手続き期限は帰国してから15日以内
児童手当の申請手続きは、帰国後15日以内に行ってください。手続きが遅れると、受給できない期間が増えてしまいます。
なお海外在住中の児童手当については、さかのぼって受給することはできません。日本に居住している人向けの制度なので、海外在住期間は支給対象外となりますよ。
児童手当 海外赴任に関するQ&A

最後に、海外赴任中の児童手当について気になる質問に回答していきます。
Q1)両親以外が児童手当を受給することも可能?
家族によっては、両親が海外転出し、子どもは日本に残るというケースもあるでしょう。その場合は日本で子どもを養育する人、たとえば祖父母などが児童手当を受給することも可能です。
この場合、必ずしも同居している必要はありません。たとえば子どもが寮生活などで祖父母と別居していても、児童手当は支給されます。
そのためには、父母が海外転出する前に祖父母を「父母指定者」として届け出ておくことが必要です。指定者になって初めて、祖父母が児童手当の申請手続きを進められるようになります。
Q2)児童手当の申請手続きが遅れるとどうなる?
児童手当の申請手続きが遅れたからと言って、ペナルティが課せられることはありません。ただし児童手当の支給が開始されるのは、請求日の翌月分から。さかのぼって請求することもできないため、申請手続きが遅くなると受給できる金額が減ってしまいます。
出生日や転入日が月末の場合は、その翌日から15日以内に申請することで、請求日ではなく出生日・転入日の翌月分から受給可能です。
たとえば6月30日が出生日の場合、7月15日までに申請すれば6月中の申請として扱われ、7月分から支給対象となります。一方で申請日が7月16日になると、7月中の申請となり、8月から支給対象となってしまいます。早めに手続きを済ませましょう。
Q3)単身で海外赴任する際に必要な手続きはある?
海外赴任が決まっても、何をすればよいかわからず悩む人は多いでしょう。海外転出届の提出や児童手当の受給者変更だけでなく、以下の手続きも忘れずに行ってください。
運転免許証の更新
海外で使わないサブスク等の解約
郵便物の管理 など
海外転出届を提出すると、住んでいる自治体の住民票から削除され、非居住者の扱いになります。ただし郵便物は封筒に書かれた住所へと配達されるため、住所変更をしない限り届き続けます。
家族に代理で受け取ってもらうこともできますが、自分で中身を確認したいという方はクラウド私書箱などのサービスを活用するとよいでしょう。たとえばメールメイトを使えば、どこにいても郵便物の受け取りが可能になります。
児童手当は海外赴任中も受給可能!条件を確認しよう

本記事では児童手当について、海外赴任中の扱いや申請手続きの方法などをケースごとに解説しました。受給者が単身で海外赴任する場合は、受給者の変更を行うことで引き続き児童手当を受給できます。条件を満たせば子どもが海外留学する場合も児童手当の対象となるので、うまく活用したいですね。
さらに両親が海外赴任する場合も、父母指定者を届け出ることで指定者が児童手当を受給できます。手続きが遅れると支給されない月が発生してしまうので、早めに手続きを行いましょう。
海外赴任中の郵便管理には「メールメイト」

海外赴任中は、郵便物の管理に悩むことも多いでしょう。日本に残る家族に受け取ってもらう、実家に転送するなどの方法もありますが、自分で郵便物の中身を確認するまでに時間がかかるのが欠点。そんな時には、どこからでも郵便物を確認できるクラウド私書箱がおすすめです。
メールメイトはクラウド私書箱の一つで、紙の郵便物をPDFデータとして確認できるサービスです。日本に届く郵便物をタイムラグなしに受け取れるため、郵便物の管理がスムーズになりますよ。さらに請求書の支払い代行もできるので、いざという時も安心です。
30日間は全額返金保証が適用されるので、ノーリスクでお試しも可能。ぜひ活用してください。
クラウド郵便MailMateを使うと、世界中どこにいても紙の郵便物をリアルタイムにパソコン・スマホ上で受け取ることができます 🙆♀️
あわせて読みたい:
郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?
クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。

