会社の書類整理が進むアイデアを紹介!書類の分類方法も詳しく解説
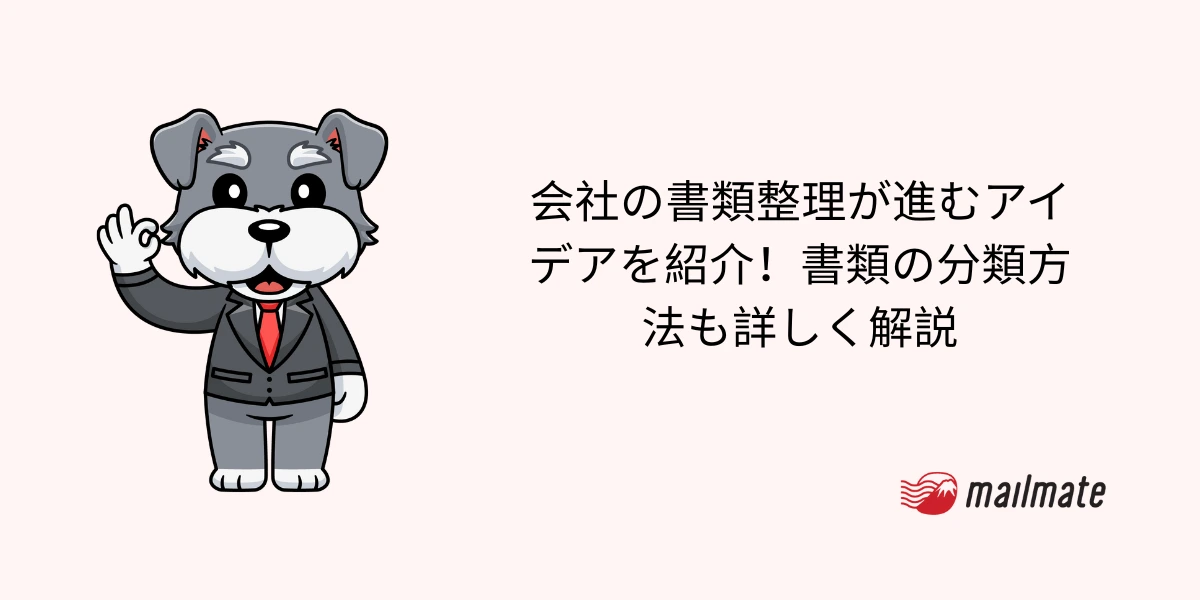
「オフィス内に書類が溢れていて狭い」
「必要な書類がどこにあるのかわかりにくい」
「会社の書類整理が進むようなアイデアがわかない」
こんな悩みを抱えている方には、この記事が参考になるでしょう。
仕事をしていると、どうしても書類は増えていきます。けれどもオフィスが書類で溢れていると、必要な書類をスムーズに見つけることができません。私も経験がありますが、必要な時に必要なものが見つからない状態は、ストレスが溜まってしまいますよね。
そこで本記事では、会社の書類整理を進めるためのアイデアや、おすすめのアイテム・ツールをご紹介します。書類の分類方法や書類整理の流れも解説するので、ぜひ実践してみてください。
クラウド郵便MailMateが、会社の郵便物の受け取り代行・スキャン・PDF化・管理画面へ配信いたします。利用開始から30日間は全額返金保証付き 🎉
書類整理をすることで業務効率化につながる
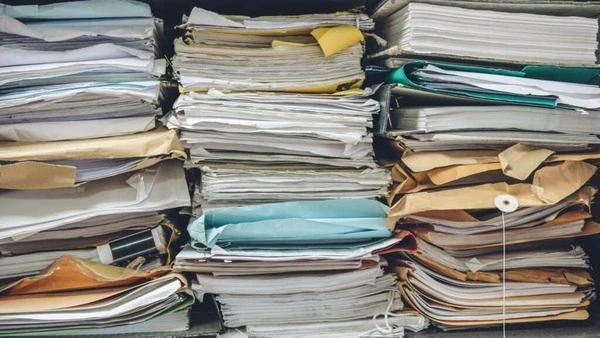
仕事をしている時に、必要な書類が見つからずに慌てた経験のある方は多いでしょう。場合によっては相手を待たせることになりますし、「書類を探す」というムダな業務が増えてしまいます。
2017年にコクヨ株式会社が行った調査によると、書類を探している時間は1日あたり約20分、年換算すると約80時間にも上るとのこと。これだけの時間がムダになっているのはもったいないですが、逆に考えると、この時間を削減できれば業務効率化につながるということになります。
また書類整理が重要な理由は、業務効率化だけではありません。いくつか見ていきましょう。
参考:書類を探す時間は“1年で約80時間”(コクヨ株式会社)
会社の書類整理が重要な理由
書類を整理しておくと、書類を探すというムダな業務が減り、効率よく仕事ができます。そしてデスク周りやオフィス内が片付くため、作業スペースを広くとることも可能になります。またスッキリした環境だと、集中力も高まるでしょう。
そしてセキュリティリスクを下げられる点も重要です。もし書類が整理されていなければ、書類の紛失や放置が増え、情報漏洩などセキュリティ面のトラブルにつながるかもしれません。書類を整理しておけば、こうしたトラブルを防止できます。
不要な書類を見極めるにはナレムコの法則が役立つ
アメリカのナレムコ(国際記録管理協議会)の統計に基づいた法則の一つに、「ナレムコの法則」があります。これは書類の利用頻度を調査したもので、以下のような結果が出ています。
一度作成された書類のうち、半年後に見返すものは10%しかない
1年後にも見返す書類は、作成した書類の1%に過ぎない
つまり99%の書類は、作成から1年経つと不要になるということです。そのためナレムコの法則に基づくと、法的に保管が義務付けられている書類を除き、ほとんどの書類は1年で廃棄して問題ないはず。しばらく書類を処分していないのであれば、不要な書類が保管スペースを占領しているかもしれませんよ。
会社の書類を整理する流れ

会社の書類整理は、以下の流れで行います。
すべての書類を取り出して分ける
書類の保管場所を決める
使用後は保管場所に戻すと決める
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1)すべての書類を取り出して分ける
一部の書類だけ整理してしまうと、後から処分に困る書類が出てきて、うまくいかなくなります。うまく整理するためには、まず引き出しやファイルなどから、書類をすべて取り出してください。
出した書類は分類し、必要な書類のファイリングを行い、不要な書類を処分します。裏が白い紙があれば、再利用してもよいですね。
ただし個人情報や機密情報の記載された書類は、そのまま処分してはいけません。必ずシュレッダーにかける、溶解するなどの対応をしましょう。
2)書類の保管場所を決める
手元に残しておく書類は、保管場所を決めておくことが大切です。書類の用途によって個人のロッカーやデスクに保管する書類もあれば、共有ロッカーや倉庫に保管するものもあるでしょう。特に重要な書類は、鍵付きの書庫やキャビネットなどで安全に保管してください。
保管期限がある書類は、この時点で「20XX年〇月まで保管」などとメモしておくと、処分の時に悩むことがありません。
3)使用後は保管場所に戻すと決める
書類が整理された状態を保つためにも、書類を使った後は元の場所に戻す習慣を付けましょう。会社全体のルールとして決めておくことで、きれいな状態をキープできます。
書類の置き場所を明示しておけば、スムーズに元の場所に戻せますよ。
会社の書類整理には分類が重要

書類を整理する際は、必ず「分類」という作業が必要です。分類の仕方はいくつかありますが、主な分け方は以下の3つです。
要・不要
使用頻度
内容
ここでは、それぞれの分け方について解説していきます。
1)書類の要・不要で分ける
まずは書類全体を「必要かどうか」という視点で分けましょう。不要な書類とは、保管期限の切れた書類や重複している書類、差し替え前の書類など。意外と処分されずに残っているものがあるはずです。
もし処分すべきか悩む書類があったら、期限を決めて保管しておくのもよい方法です。期限内に使うことがあれば必要な書類として保管し、期限が切れるまで使わなければ処分してくださいね。
2)使用頻度ごとに分ける
書類を使用頻度ごとに分けておくと、効率よく保管できます。たとえば高頻度で使う書類であれば、取り出しやすい場所に保管しておくと便利。できれば腰から上の高さに置いておくと探しやすく、取り出す際も体に負担がかかりません。自分だけが使うものなら、個人デスクに置いておくのもよいでしょう。
一方、使用頻度がそう高くない書類であれば、倉庫やロッカーに保管し、必要な時に参照できる状態にしておけば十分です。ただし機密性の高い書類は鍵付きの場所に保管して、セキュリティを強化してください。
3)書類の内容によって分ける
同じ場所にいくつも書類を保管する場合は、年度ごとや部署ごと、プロジェクトごとなど、書類の内容別に分けて保管します。保管の際は、以下のようなアイテムを使うと便利です。
クリアファイル:透明で薄型。書類の持ち運びにも便利
クリアブック:透明のポケットが付いた冊子型のファイル。書類を出し入れしやすい
フラットファイル:穴を開けて綴じていく薄型のファイル。値段が安い
リングファイル:穴を開けて綴じていく大型のファイル。書類をめくりやすい
保管する書類の量や置き場所、持ち運ぶ頻度などに応じて、適するアイテムを選びましょう。
関連記事:会社全体の生産性向上!メール室業務を効率化する3つの方法
会社の書類整理に役立つアイデア3選

せっかく書類の整理をしても、使いにくいとキレイな状態を保つことができません。ただファイリングして保管するだけでなく、使いやすく収納したいところです。
ここでは書類整理のコツやアイデアを紹介します。ぜひ参考にして、さらなる業務効率化を図ってください。
1)書類を立てて保管する
書類を立てて保管するのは、整理術の基本です。書類を平置きにしていると、どんどん書類が積みあがり、探しづらく取り出しづらい状態になってしまいます。書類が重なっていると、破損や紛失の原因にもなりやすいので注意が必要です。
また紙は日光や湿度・温度など、周囲の環境によって劣化しやすいもの。直射日光の当たる場所や湿度の高すぎる場所、極端な温度変化が起こる場所を避けて保管しましょう。
2)ファイルのラベルを工夫する
ファイルを収納する際は、ラベルの工夫も大切です。背表紙にどんな書類がファイルされているのか明記し、いちいち中を確認しなくても目的の書類が見つかる状態にしておきましょう。可能であれば色分けもしてあると、直感的に区別できるため便利です。
また使用したファイルを戻しやすくするために、以下のような工夫ができます。
複数のファイルをまたいで、斜めの線やイラストなどを入れる
ファイルと置き場所に同じ色・番号を付けておく
写真やイラストで内容を表示しておく
ラベルの準備には時間がかかりますが、その後の使いやすさが大きく変わります。できるところから取り入れてみるとよいでしょう。
3)ペーパーレス化を進める
ペーパーレス化を進めることで、紙で保存する書類の量を減らせます。それによって、以下のようなメリットが得られます。
書類をファイリングして収納する手間が削減できる
書類の印刷コスト、郵送コストなどを削減できる
書類の保管場所が少なく済む
リモートワークがしやすくなる
2005年にはe-文書法が、2021年には改正電子帳簿保存法が施行されるなど、日本の企業内でも着実にペーパーレス化が進んでいます。業務効率化の大きな一歩となりうるので、この機会にペーパーレス化を進めるのもよいでしょう。
ペーパーレス化を進める際の注意点
ペーパーレス化にはメリットが多い反面、注意点もあります。
ツールの利用にコストがかかる
ITスキルの低い従業員にはハードルが高い
システム障害の影響を受けやすい
資料全体の把握がしづらい
ペーパーレス化を進めるためにツールやシステムを導入する場合、コストがかかります。また従業員によってITスキルに差があると、使いこなせる人とそうでない人の差が出る点にも注意してください。
またシステム障害が起こると、データ破損などのリスクがあります。こまめにバックアップをとるなどの対応策が必要です。
そして画面のサイズによっては、資料の全体像が把握しづらくなります。長く画面を見ると眼精疲労の原因にもなるでしょう。
ペーパーレス化におすすめのツール

メールメイトは、紙の郵便物をクラウド上で管理するサービスです。利用方法は、以下のとおりです。
メールメイトの住所宛に郵便物が届く
郵便物がスキャン・データ化される
クラウド上で郵便物データを確認する
メールメイトを導入すれば、会社宛の郵便物が紙ではなくPDFデータとして届くようになります。手作業で郵便物をスキャンする必要がないので、これからペーパーレス化を進めたい企業におすすめです。
また新しく届いた郵便物をデータ管理するだけでなく、既存書類をデータ化してアップロードすれば、まとめて管理することが可能です。電子帳簿保存法に対応しているほか、Pマーク認定も取得しているため、安心して利用できますよ。
クラウド郵便メールメイトが、会社の郵便物の受け取り代行・スキャン・PDF化・管理画面へ配信いたします。利用開始から30日間は全額返金保証付き 🎉
関連記事:
会社書類整理アイデアに関するQ&A

最後に、書類整理についてよくある質問に回答します。
Q1)書類整理に役立つアイテムには何がある?
書類を立てて保管するには、ファイルスタンドやファイルボックスがおすすめです。

引用:ポリプロピレンスタンドファイルボックス・A4用・ダークグレー | 無印良品
斜めにカットされていて取り出しやすいもの、持ち手が付いていて運びやすいものなど、さまざまな商品があります。
ファイルにラベルを付ける際は、テプラやマスキングテープ、ラベルシールなどを使うと便利でしょう。貼り直しができるタイプを選べば、ファイルの中身を変えた時もキレイに使い続けられます。
また数種類の書類をまとめてファイリングする時は、インデックスを活用します。
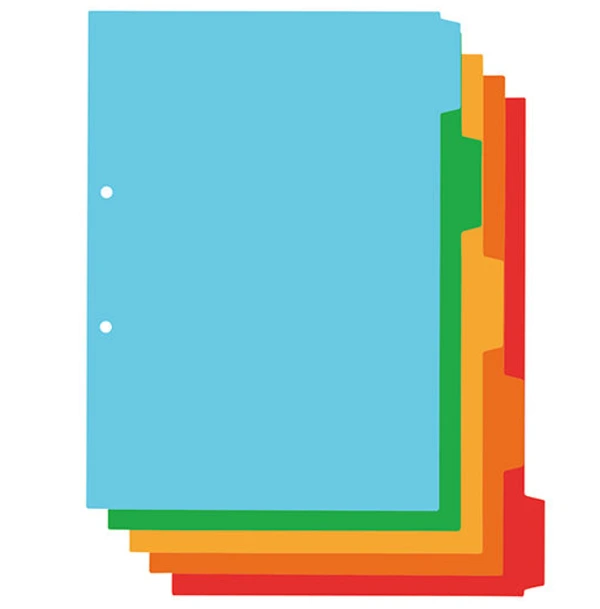
引用:アスクル カラーインデックス A4タテ インデックスシート 2穴 5山 PP製 1組 オリジナル - アスクル
インデックスがあれば書類が探しやすくなりますし、見た目も整います。シートタイプとシールタイプがあるので、使いやすいほうを選んでください。
Q2)ペーパーレス化を進める方法は?
ペーパーレス化を進めるには、少しずつ段階を踏む必要があります。いきなりすべての書類をデータに移行することはできないので、まずはどの書類から始めるのか決めましょう。請求書や納品書などをデータ移行するには他企業との連携が必要なので、社内で使うタイムカードや給与明細から移行するとよいですね。
対象の書類が決まったら、新規書類をデータとして作成・保管するようにします。新しく業務フローが確立できたら、既存書類のデータ移行を始めてください。スキャンやOCR技術を活用することで、スムーズにデータ移行ができるはずです。
Q3)書類データを保管する時の注意点は?
電子帳簿保存法によると、保管するデータは大きく3種類に分けられます。
電子取引:メール等でやり取りしたデータ
電子帳簿・電子書類:会計ソフト等で作成したデータ
スキャナ保存:既存書類をスキャンしたデータ
それぞれに保存要件が定められており、それに沿って保存しなければなりません。たとえばスキャナ保存には、次の要件があります。
解像度は200dpi以上
赤・緑・青色の階調は256階調以上
タイムスタンプの付与
取引年月日、取引金額等による検索性の確保 など
こうした要件を確認してから、データ移行を進めてください。
また書類データも、適宜ファイル整理を行う必要があります。保管期限が切れた書類は、忘れずに処分しましょう。
オフィスの書類整理を行って業務効率化につなげよう

本記事では、会社の書類整理を進めるためのアイデアやおすすめのアイテムなどをご紹介しました。書類整理を行うことで、「書類を探す」という時間がなくなり、集中力アップにもつながります。業務効率化ができるだけでなく、書類紛失などのリスクも下げられますよ。
書類整理を進めるには、ペーパーレス化も有効です。書類をデータで扱うようになれば、ファイリングの手間や、書類の保管スペースを削減することができるでしょう。
ペーパーレス化を進めるには、紙で受け取った書類をクラウド上で管理できるメールメイトが便利です。新規書類だけでなく、自社でスキャンした書類との一元管理も可能。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。
クラウド郵便MailMateが、会社の郵便物の受け取り代行・スキャン・PDF化・管理画面へ配信いたします。利用開始から30日間は全額返金保証付き 🎉
おすすめ記事:仕事を効率化する!オフィスの書類整理のコツと習慣を紹介
郵便物を受け取るためだけに帰宅や出社してませんか?
クラウド郵便で世界中どこにいてもあなたに届く紙の郵便物をリアルタイムにオンラインで確認することができます。

